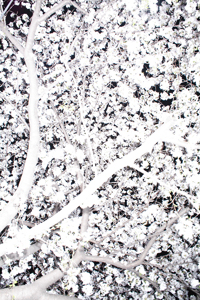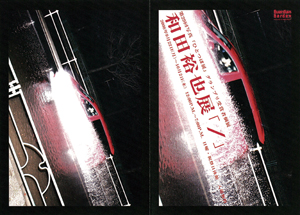1年前の『ひとつぼ展』では、黒いアクリルのラックのなかにハガキサイズの写真をしまいこみ、鑑賞者にその写真を自由に観て持ち帰ってもらうという独創的な展示をした和田裕也さん。そこに収められた、ストロボをたいて夜の風景を写した379枚の写真は、デジタルカメラで撮影したものの中から選んだものでした。公開二次審査会では「写真にキレがある」「なにがでてくるかわからない未知なる気迫を感じる」と評価され、みごとグランプリを獲得しました。今回のインタビューでは、最初に興味を持った映画の話から、写真との出会い、そして現在に至るまでを伺いました。
映画の専門学校時代、そして写真との出会い
高校生の時に「Pulp Ficion」のような暴力的だけどしっかりと構成力があるエンターテインメントの映画を見て、映画の面白さを知りました。海外だけでなく日本の映画はどうなんだろうと思い、北野武さんや、岩井俊二さん、青山真治さん、大友克洋さんなどの作品を見ていくうちに、日本映画のすごさを感じました。自分もやりたいなと思ったのは、その頃からです。映画の専門学校に入り、映画のことを一応トータルで学んだんですけど、広く浅くみたいな感じでなかなか実践にならなくて。自分のイメージはすごくあるけれど、それを形にするにはどうしたらいいのか分からなかったんです。就職を決めなければならない時期になり、就職課で撮影や編集関係の仕事を探しましたが、なかなか決められませんでした。「何かを伝えるということにとどまらない」ことを目的とする映画とは、紹介されたどの仕事もかけ離れてるように思えてしまって。写真の経験はなかったんですが、求人情報誌で冠婚葬祭のスナップ写真を撮る仕事をみつけて、とりあえずそこに行こうと思いました。入ってみたら、葬式の撮影ばかりを、36枚撮りのフィルム2本に、祭壇や遺影、御焼香、お坊さん、お別れの挨拶、見送りといった告別式を収めるんです。始めたばかりの頃はうまく撮れなくて。撮れる枚数も限られてますし、撮り直しもできない。失敗したことを克服できないまま、次の撮影をこなさなければいけないという葛藤を抱えながら半年。ようやく感覚をつかんできました。すると、周囲からも認められるようになって。かなり撮れてるなという感覚、写真の面白さは最初にそこで学んだんです。
スタジオマン、アシスタントを経て、フリーに
写真の仕事でさらにステップアップしたいと思い、六本木スタジオに入り、スタジオマンとして一年半くらい働きました。スタジオでは、ファッションや広告の分野など、プロのライティングやフォトグラファーの仕事の基礎を学べたことがとても勉強になりました。その後、広川泰士さんのアシスタントを1年半くらいさせていただきました。広川さんはとてもパワーがある方で、仕事も作品制作も絶対に手を抜かない。自分もアシスタントをやっている間、いつも緊張していました。特に、どこまで写真を追い込むか、を学ばせていただいたのだと思います。フリーになってからは、自分の作品というよりは、仕事として写真を撮りたいという思いがありました。仕事がとれるように、やわらかく撮った写真でポートフォリオをつくって、デザイナーのところへ営業に行ったり。でも、見る側のことを考えすぎて、写真がデザインに寄ってしまったと思うんです。結局誰にでも撮れる写真になってしまっていて。デザインのための写真じゃなくて写真のための写真をしなければと感じました。それで1年前の『ひとつぼ展』に応募した写真とかにつながるんです。
自分と写真との距離
『ひとつぼ展』に出品した作品は、自分でも説明がつかないもの、言葉には出来ないものをあえて写真に収めようとしていました。デジカメのシャッターを無意識にきることで出てくる、自分の予想も超えた写真を、何万枚の中から選びとる写真/映像。今までで一番写真と自分との距離が近いものだったと思います。でもその結果、写真と近づきすぎてしまって、閉鎖的なものになってしまったと今は、とても反省しています。これからは、ブレない強い思いで開かれた写真を撮れるように、どんどん撮っていきたいと思います。

和田裕也
1978年生まれ
[受賞歴]
エプソンカラーイメージングコンテスト2006写真部門 優秀賞
第29回写真『ひとつぼ展』グランプリ