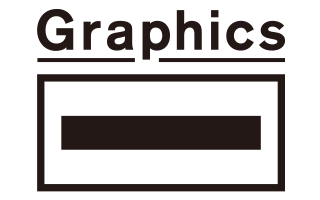YOSHIDAYAMAR(吉田山)
富山県出身アルプス育ち。手段と目的が混在した散歩という方法を用いてフィールドワークに勤しむ。そのアウトプットとして、展覧会企画や様々な制作を行う。
ウェアラブル・新たなる・廃墟
本来は打ち捨てられた建物を指す言葉“廃墟”を蝶番とし、アーティスト・平手による個展「拳に綿を詰める」へ向けた解釈の可能性の薄皮を剥いでいこうと思う。
今ではこのような場所での展覧会は普通であるが、七〇年代後半に都市の中で見捨てられた廃屋を利用し、そこをアート・スペースとして再活用していくという発想は新鮮であった。『アートレス―マイノリティとしての現代美術 (ArtEdge)』増補改訂版 川俣正著 p127
1970年後半、学生時代の川俣正は雑誌でニューヨークにある「P.S.1(Public School 1)」という廃小学校を利用したアートスペースの存在を知ることとなる。その“廃墟”の可能性に抱いた思いを振り返り上記の書籍に記している。現代では“廃墟”を一時的に展覧会のために利用することは方法の一つとなり様々な展覧会が開催されている。このテキストではこのような物体としての“廃墟”ではなく、ベクトル違いの概念としての廃墟、仮に<√廃墟>とする。
「拳に綿を詰める」の会場であるギャラリー「ガーディアン・ガーデン」に入場すると、まずは人感センサー付きの立体作品が反応し、ノイズ混じりの音声が流れる。ノイズ混じりの音声は『いらっしゃいませ』と流れているらしい、はっきりとは聞き取れない。この布で作られた立体作品は崩れてしまったような笑顔で鑑賞者を出迎えてくれる。まるで宮崎駿監督「天空の城ラピュタ」での空に浮かぶ城で出会うロボット兵のようである。また、この展覧会は作品全て接触可と記載されており、通常の展覧会では禁止されている作品への接触が認められている。細やかに展覧会の脱領土化すらも同時に行われているという点を記憶に残しておこう。
会場には段ボールや紙などで作られた昭和感のある町角を想起させる書き割りがあり、その町には様々な具体的な人体のような形状の立体作品が佇む。これらは布でできているのでソフト・スカルプチャー*と呼べるだろう。アートの単純な脱領土を図るために接触可としているのではなく『物は壊れる定め→修復します』という態度によって接触を認めていることはアーティスト・平手がファッションデザインの塾「coconogacco」で学んでいたことが要因とされる。
*彫刻作品を石やメタルなどの硬い素材ではなく、布やビニールなどの柔軟な素材で制作された立体作品を指す。「ソフト・スカルプチャー」の原点と言われるクレス・オルデンバーグの作品の一つには「ソフト・ベースボール・バット」(1967年)という野球のバットを模した立体作品があり、このバットを街中で振り回すパフォーマンスをしていたとの記録がある。今回のテキストでは余談となるが、平手も野球のユニフォームを模した衣装を制作しパフォーマンスしている。
この展覧会を構成するソフト・スカルプチャーは壁面にプロジェクションされている記録映像を見ると実際に着用できることが開示されており、服さながらのウェアラブルさを有しているソフト・スカルプチャーだということ、そして、接近してみるとミシン作業と手縫いを駆使して丁寧に作られていることがわかり、このディテールによって接触可という言葉は単なる展覧会や美術制度へのアンチテーゼではないことがわかる。接触し、汚れた/壊れたとて、洗濯や修復が可能であることが見て取れる、このソフト・スカルプチャー自体がスタティックなものではなく変化するプロセスを内包し続けている。そもそも、建築物としての“廃墟”もプロセスの途中であり、リノベーションされ再度利用されることで“廃墟”ではなくなる可能性も秘めているということを再認識させる。
会場の奥には段ボール等で作られたアーティスト・平手の家を模したレジデンススペースがあり、作家が在廊の際はそこでドローイングや漫画作品等を制作している、展覧会にプライベートエリアを作ることによってソフト・スカルプチャーだけではなく展覧会自体をもウェアラブルな立体作品として身に纏ってしまおうという一貫した態度はまさにファッションの拡張かつ、“家/住居”の拡張なのではないだろうか。
「もし、災害や戦争、失業などで家をなくしてしまった人々に、ファッションデザイナーである私は、どんな服を提案できるのか、またその服は平和なときにはどんな姿をしているのか」
FINAL HOMEは表生地と裏生地の隙間を収納スペースとして活用する事で日常と非常時に対応する都市型サバイバルウエアーです。隙間に新聞紙を詰めれば防寒着に、予め非常食や医療キットを入れておけば災害時に対応します。家という安心を着る例えから「究極の家」『FINAL HOME』と名付けました。
津村 耕佑 (https://www.kosuketsumura.com/finalhome-archiveより)
災害時等の極限状況下でのサバイバルと日常での服を一つのプロダクトで両立させることをミッションに掲げるファッションブランド/プロジェクト「FINAL HOME」のコンセプトである「究極の家」によって服が概念的な建築物だと解釈する脈絡を接続すると、服の<√廃墟>も存在していることになる。服が展覧会に陳列されウェアラブルな機能を一時的に取り上げられ、宙吊りにされた状態を<√廃墟>と呼ぶこととすると、この展覧会では二重に<√廃墟>が掛け合わされ、実際の建築的なベクトルの“廃墟”が誕生することになる。
平手のウェアラブル・ソフト・スカルプチャーは実用性という軸では「FINAL HOME」の機能的な提案とは対極にあるとも見えるが、そのコンセプト同様に服を“家/住居”へと拡張する場合には、同じ座標に位置し、どちらも“家/住居”の概念を身に纏い、自身を世界へと開いていく術を模索している。それは“家/住居”への期待が時代によって変遷してきたことにも関係していると考察できる。1970年代以降に“廃墟”を活用した展覧会が盛んになったこと、そしてインターネットが一般的に普及するにつれてイメージの共有の利便性の向上との結びつきによって特殊な環境での写真撮影が一種のエンターテインメント化し、“廃墟”が不気味なものから見栄えの良いものへと変化したと考えることができる。それとともに景気の悪化や新型感染症によって“家/住居”に求める豊かさの変化も関係している。そして、この展覧会自体が現代における居心地の良い「究極の家」もしくは“廃墟”の一つのバージョンなのだろう。