美術評論家の光田由里さんをゲストに迎え、トークイベント「写真を通した3人の距離感」を開催しました。

光田由里(美術評論家)
戦後美術史/写真史研究。京都大学文学部卒業。多摩美術大学教授。著書に『高松次郎 言葉ともの』(2011年/水声社)、『野島康三写真集』(2009年/赤々舎)、『「美術批評」誌とその時代―』(2006年/Fuji Xerox Art Bulletin)、『写真、芸術との界面に』(2006年/青弓社、日本写真協会学芸賞)など。企画展覧会に「美術は語られる 中原佑介の眼」(2016年)、「The New World to Come Experiments in Japanese Art and Photography,1968-1979」(2015年)、「ハイレッド・センター 直接行動の軌跡」展(2013-4年)ほか多数。

池崎一世
女子美術大学絵画科洋画専攻卒業。
NY市立大学ラガーディアコミュニティーカレッジ メンタルヘルス科卒業。
第5回写真「1_WALL」ファイナリスト、Culture Centre参加。

佐藤麻優子
専門学校桑沢デザイン研究所中退。第14回写真「1_WALL」グランプリ。
個展「ようかいよくまみれ」ガーディアン・ガーデン/東京、個展「ようかいよくまみれ」excube/大阪、「代官山フォトフェア2017」代官山ヒルサイドテラス/東京、個展「生きる女」VACANT/東京、グループ展「dix vol.3」QUIET NOISE arts and break/東京、個展「繋がってください」KKAG gallery/東京、グループ展「Culture Centre in flotsam books」flotsambooks/東京。

染井冴香
武蔵野美術大学映像学科メディアアート専攻卒業。第13回写真「1_WALL」ファイナリスト。「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD 2016」光田由里賞、「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD 2017」準グランプリ。POST/PHOTOGRAPHY 2020(アートビートパブリッシャーズ)掲載。

トークイベント ログ
光田:聞き役の光田と申します。今日はがんがんお話しお願いしますね。最初にこの3人展を今日拝見して、会場に入って言いたいことがこんなに沢山ある会場ということに、まず圧倒されました。見ていたら本当に面白くて、これは皆さま絶対に見逃さないでください。この展覧会を見る人の中にも言いたいことがいっぱい生まれてくるような、そんな展覧会だなという第一感です。感想は追い追い申し上げるとして、まずこの3人は元々のお友達でもパッと見なさそうだし、どんな感じで始まったんですか?
佐藤:一番最初の出会いは、自分の「1_WALL」のグランプリ個展の会場でした。私は「1_WALL」に応募する際に過去の審査会レポート*を読んだことで2人のことを知り、当時は特に池崎さんの写真に共感して、個展の際にトークをお願いしたのですが、それを染井さんが聴きに来てくださっていて。その際に染井さんが作品集を持って来ていて、みんなで写真観ながら話しました。トークイベントのあとガーディアンの方がみんなで食事に連れていってくださって。それが一番最初の出会いです。
*池崎一世/第5回写真「1_WALL」審査会レポート
*佐藤麻優子/第14回写真「1_WALL」審査会レポート
*染井冴香/第13回写真「1_WALL」審査会レポート
光田:そうやってガーディアン・ガーデンを通して3人が知り合ったということなんですけども、知り合ったことと一緒に作品を作ることには、ちょっと段階がありませんか?
染井:そうですね。最初に3人で会った時に、「なんだろう、いいな」って思ったのと、それ以上に「このあと何かあるな」という気持ちが自分の中であって。いいって思う写真があると思うんですけど、それ以上に繋がってるみたいな。多分頭のどこかの感覚が一緒なんだなという気持ちがあって。その後、池崎さんからお誘いいただいて2人でご飯食べている時に「一緒にできたらいいね」って話していて。
光田:それで、じゃあなんかやろうとなったわけですね。
池崎:はい、そうです。
光田:自分の作品と、今回の作品は違いますよね?今まで撮影した作品と繋がっているけれども、途中でジャンプもきっといっぱいあったと思うんですが。
佐藤:そうですね。多分最初一番戸惑いがあったのは自分かも。個々で成果物を出すグループ展は経験ありましたが、コレクティブという形は初めてでしたし、あまり人と何かをすることが得意じゃなかったので。制作の仕方も池崎さんと染井さんの方が似ているかも。
自分はどちらかというと撮影前に考えを言葉を少しまとめてから撮影する形が多いのですが、二人はそうじゃなくて、より抽象的にイメージを写真にしていくことからスタートして進めていく感じだったので、今回はそのやり方に乗せてもらった感じです。
光田:今までとは違う、まずパフォーマティブに始めるみたいな感じですかね。
池崎:佐藤さんとのトークの後の食事がすごい雰囲気が良くって、なんとなくエネルギーみたいなのがそこにあったんですけど。私と佐藤さんの一番最初のつながりも、全然人を知らないところでとくに説明っぽい内容でもない写真だけ見てなにかしらの共感がありました。
個人的に気になる写真って皆さんそれぞれあると思うんですけど、写真のイメージを通して繋がったっていうのが特徴的かなって思っていて。実際知り合って会話をしてみたら、結構共感する生い立ちだったり、家族のテーマの会話もすごい共感することが多かったんですけど。
そこで、あぁこんなに経験のことで、(佐藤さんと染井さんは歳は近いけど私は結構離れてる中で)、写真を通して知り合って、現実の出来事で共感することがいっぱいあるんだってことにすごく驚きました。で、そこから自然に制作に結びついてきました。
光田:共感する写真のイメージだけではなく、体験とか自分達の問題とかがスムーズに入ってきたんですか?
佐藤:ガーディアン・ガーデンの方に関わっていただく以前から制作していて、その時は割とこう、言い争いまではいかないんですけど、ぶつかることもありました。自分が人間として足りない部分で迷惑かけたりしたこともあったし、友達という関係性でもなければそれぞれ生活環境も違うので、会話のリズム感や言葉の使い方も違ったりして、最初は(やりとりも制作も)ちょっとぎこちない感じがあったかな。
池崎:一番最初に写真を撮ろうとなった時はやはりかなり手探りでどうやって制作していく?みたいな戸惑いはありました。
私はとりあえずのテーマやイメージみたいのからセットアップを作って、写真が出来上がってみたら、ちょっと自分の無意識な部分も見えるみたいなプロセスだったり、一方佐藤さんはさっき言ってたみたいにきっちりシチュエーションだったりを言語化してからこういうものをしっかり撮りたい、私よりももっとしっかりしたプランっていうかコンセプト組んでて、でもその辺を上手く折衷して。とりあえず撮ろうっていう場所決めから始めますね。ロケーションから。
光田:染井さんは、どうですか。
染井:3人で撮影する時は、全然違うところに住んでるから大変というのもあるけど、撮影自体始まってからは、初めて会ってからは3回目とか2回目とかだったんで、どういうふうに話を進めるのかなとか思ってたけど。撮影ってやっぱ、異世界っていうか、現実じゃないから、自由っていうか、各々撮ってる感じであまり違和感なかったです。
光田:それで3人の制作が進むにつれて、ガーディアン・ガーデンで展覧会をやる話も出て、どんどんスピードアップしていったイメージでいいですかね。全体でどのくらいの期間ですか、この制作期間は。
染井:2年か、3年くらいかな。

光田:(展示している作品を見ながら)これは時系列で並んでいるのではないですよね。入ってすぐこちらの壁(入口左側の壁)からぐるりと展開して最後の写真で終わるって感じなんですけど、最初に作った写真ってどれですかね?
佐藤:一番最初は2人が撮った写真で、染井さんが悪魔の羽をつけてる3つ窓があるマットの写真(No.29)なんですけど、その時私が参加できてなかった撮影が一番最初の写真かな。
池崎:この作品(No.10)も同じ時に撮りました。
-

No.29 「want black」2021、染井冴香
-

No.10「family」2020、池崎一世
染井:そうだ、はい。全然テーマもあんまり考えてなかった時で、私はその時期にNetflixのアニメを見て悪魔がめっちゃ可愛い、すごいって思ってて。自分も変身したいなという感じで考えてたんですけど。
池崎さんは自分と撮影することになって、撮りたいって考えてくれてた作品なんですけど、これ(No.10)は家族のことについて撮られた作品で……すいません、池崎さん。
池崎:今染井さんさらっと流しちゃったけど、この悪魔の話はもっと深い話が実はあります。
撮影は同じ場所だけど、ディレクションが私だったり、染井さんのディレクションで撮ったり、結構バラバラに撮ってて、だから名前とタイトルも全部別々なんです。
光田:そういうことか。だからこのハンドアウトでは、3人展で一緒に撮ってるのに、一作品一人の作家の名前がクレジットになってるんですね。ちょっと不思議だったんだけど、それはディレクションってことなんですか?
池崎:そうです。
光田:つまりこういう作品を作りますと言った人がいて撮影して、結構厳密に分けてるんですね。これは誰のって。
佐藤:実際にシャッターを押している人と画角を決めている人は別の人っていうパターンの写真もあります。どういうものを撮るかディレクションをしている人を記名するのが、これは染井さんの写真だなとか、池崎さんの写真だな、としっくりきている感じ。
光田:3人の中では、写真に個性がはっきり出てるっていうイメージなんですね。それを織りなすようにして、全体が一つの物語と考えていいんですか?それとも色んな断片の作り出すコラージュみたいなイメージですか?
池崎:私はそれは全然見てくださる方の自由に任せたいんですけど、創作のプロセスから言ったら断片の集まりとも言えますね。もともと一つのストーリーという形ではないです。でも関連性が一個ずつあって、3人の会話が元になっています。
佐藤:今の池崎さんの意見がとても腑に落ちています。ただ展示の構成で写真を並べるときは全体のストーリーも意識しているから、自分の中では曖昧な感じかも。
池崎:実際撮影を進めてみると一人一人かなり確固としたスタンスみたいのがあって。例えば染井さんの写真、染井さんの中のストーリーっていうか、すごい撮りたい一貫したテーマがあったんだなっていうのを撮り進めていく中で感じました。出来上がってみたら、一つのストーリーだったんだって全貌が見えたというか。
染井:(展示している作品は)断片的にも見えるし、実際ストーリーに沿って撮ってたわけじゃないんですけど、この流れみたいのができた時点で、私はストーリーっぽくなってるというか、始まりと終わりが何かあったなっていうはちょっとしてるかもしれない。単純に今回家族のことについて自分はフォーカスして撮らなきゃいけないというような意思があったんですけど、それにもう終わりがつけられた感じがして。だから始まりと終わりはなんとなく自分の中ではあったかもしれない。
光田:この展示をやってみたら、その家族のテーマか区切りがついた実感があったってことですか?
染井:そうですね。生まれ直したみたいな気持ちがちょっとあります。トラウマを乗り越えるみたいな感じじゃないけど、そういうトラウマって再現するとそのことについて結構吹っ切れる。
光田:浄化されるっていうか?
染井:浄化されるって結構心理学的に言われてることだと思うんですけど、それも単純に自分で作品の中で消化できてるというか、できた感じがあって、終わったなぁって。終わってないけど、一区切りついたなっていう感じはありました。
光田:それは他のお二人も感じ取るようなところがありました?
池崎:染井さんについてですか?
光田:いや、家族のテーマみたいなことです。
池崎:個人的に?
光田:個人的にというか、私は詳しい制作の経緯はわからないけれども、全体に見てやっぱり女性のライフストーリーっていうか、いろんな段階があるじゃないですか。大人になる途中とか、なってまたちょっと戻ったりとか。色々なライフステージや、家族とかの問題、母と子みたいなイメージを結構強く感じたりしたんですけれども、そういう染井さんがやらなきゃいけないと思ってたテーマに、他の2人も感じるところはあったのかなと思って質問しました。
佐藤:染井さんが話していたトラウマから一回こう、死んで生まれ変わるみたいな感覚は、自分は他のテーマであって。それがこのあたりの3点です。この展示を通して生まれ直すと言うか、そういったところがありました。

(左から)
No.20「not belladonna」2021、佐藤麻優子
No.21&22「my puppy」2021、佐藤麻優子

池崎:私もそうですね。私は結構子どもを持って親になってから、そこを区切りにして、皆さんそう感じる方もおられるかなと思うんですけど、区切りがついてものすごく変わっちゃったような気がしてたんで。昔の自分、例えば佐藤さんや染井さんの年齢の頃の自分っていうのはすごい距離を感じていて。
でも今回の制作を通してその頃の自分との同一性みたいのを取り戻させてもらえてる気持ちがしました。あと私はひとり親でこども育ててるので、責任っていうか辛い時もあって。今回一人じゃなくて複数人で制作することを通して、その……混ざるって言い方も変ですけど、なんていうか、一人である苦しみ?みたいのは別に頭の中の幻想でもあって、複数人の、場所やものなども含めて、アイデンティティの拡張みたいな、そういう可能性というかそれが実は事実でもあるみたいな、そういうことを感じられたのが私は個人的にとても嬉しかったです。
光田:その嬉しさは見る方にも割と伝わってくるっていうか、何か楽しそうっていうのがまずあって、扱ってる問題は多分心理的なすごくリアルな問題なんだけれども、3人でやることによってファンタジーの部分が大きくなっていて。そこが楽しそうという感じに思ってたんですけど、今お話聞いてリアルさから生まれてくるファンタジーみたいなものにカタルシス効果があるのかなっていうのを見てるほうにも感じるのでね。
だから写真って本当に色んな使い方ができるわけですけれども、私の言い方がちょっとざっくりし過ぎてますけれど、女性のライフステージのようなことを、ちょっと遊びも入れて、そしてストラッグルっていうのかな。これはこうですっていう答えは別に求められてない。そうじゃなくて、問題とストラッグルしてる様子がファンタジーとして生まれ変わってるって言うか。そこに見る人はどんどんこう入って行って共有できるっていうかな。そういうような幅を感じたんですけどね。ファンタジーっていう言い方はどうですかね、あまりピンとこないですかね?
池崎:ファンタジー……、そうですね。私、今光田さんのお言葉を伺って浮かんだのは、ファンタジーと言うかイメージ世界っていうか、やっぱり写真撮る時って写真撮影に向かう時とかもちょっと現実とは違う、そういうファンタジーと言える中では自分と他人の境界と言うか、位置関係みたいのがすごくフラットになると言うか。そういう意味ですごくいいなっていうか、そういうとこなんですかね……ちょっとうまく言えてないかもしれません。
佐藤:位置関係っていうのは、役割みたいな事ですか?
池崎:役割もあるけど、何だろう。普段生活する中での、社会的な役割ですかね。無意識のレベルでの日本の社会の中で内面化された儀礼的なものだったり、個人同士の距離感?とかですかね、そういうとこなのかな。
光田:さてさて、ではちょっと具体的な作品について聞いてみていいですか?この最初の壁、この1つの壁のまとまりみたいな感じでいいですかね。
その中で私はこの作品が特に気になってるとか、ちょっと話してみたいっていうのがあったら言ってみていただくっていうのはどうですか?染井さんから。
染井:そうですね、私は、母親が亡くなってから、池崎さんから展示のお誘いいただいて。(写っているのは)母を看取った家で、15年ぐらい過ごした実家も、国の政策で公園をつくるためになくなることになって。引っ越してる時に捨てなきゃいけないようなものをどうしよう……と思っていたときに撮影した写真とか、その小っちゃい作品(No.3)は引っ越しして家族で車で移動する時に撮った写真とか色々混ざってたりします。家を失うっていう経験が2回目で、小学生の時も4年生くらいまで過ごした家が目の前で工事で潰されてるところを見て。
その時その家自体に全然思い入れなかったっていうか、家がなくなるって事自体が全然分かってなかったから、目の前でなくなった時にすごい……なんだろう……イメージとして焼きつくものが結構あって。もうあんまりこういう経験したくないなって思ったんですけど、もう一回見るのは無理だなと思いながら引越し作業とかしてて……すいません、なに話そうとしてたか忘れちゃった。
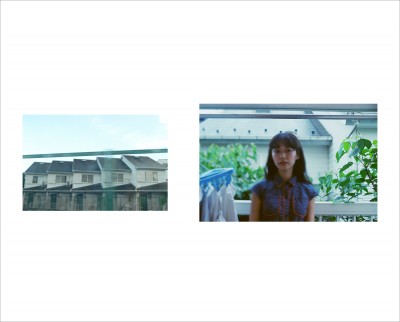
No.3「the house」2020、染井冴香
光田:この中では染井さんの役割って攻撃されてる側のようなイメージ?
染井:そうですね。単純に母親が亡くなった時に、人が死んじゃうところを見るのが初めてだったんですけど、こんな死に方ってあるのかなってすごい思っていて。死ぬ時ってこんななんだみたいな、バカみたいなこと言うんですけど。
光田:それを写真でやってみたかったんですか?
染井:その経験の後に、もう自分もずっとふわふわして。お姉ちゃんとかもぼーっとして、この家も無くなるのかなみたいなこと話したりしていて、現実味が全然ないっていうか、自分も1回死んでる感じに思って。
このイメージに落とし込もうかなって思ったんですけど、作品にするのも気持ち的にできるのか若干不安というか、作品にしていいのかな、っていう気持ちがあって。でもこうして出来上がってから見ると、意外と救われたような気持ちになりました。それまでの流れみたいな感じでちょっとここに落とし込んで(並べている)るんですけど、作品として。
佐藤:展示の構成を担当したんですけど、この壁のメインとして扱いたいなって思ってたのがその染井さんの死んでる写真で。(No.6)染井さんから聞いてた話とビジュアルとで一回死んで、新しいというか、トラウマを乗り越える的な意味合いの方を強く感じてましたが、今話を聞いて、染井さんのお母さん自体に近づく、寄り添うと言うか、歩み寄ると言うか、そういう側面があるんだなっていうのを初めて気づきました。合っているかはわかんないんですけど、そうだったんだって、ちょっとこの作品に対する理解が深まったかも。

No.6「one of the dead」2021、染井冴香

光田:染井さんはこの作品に関してはハンドアウトでもコメント結構長めに出してますよね。
染井:この作品にしようって決断したのが、映画『ヘレディタリー/継承』を見ていて、その中でジオラマ作家のお母さんがトラウマをジオラマで再現することを作品でやってたんですけど、結構グロテスクな作品でホラーの作品なんですけど。
その娘さんが亡くなってしまって、その時の光景をジオラマで再現しようとして、旦那さんにはそんなのやめろって言われたりしていて。でもその人は作品に落とし込む事によってスッキリしていて、全然ジオラマとはまた別なんですけど……。
光田:作品を見る人として、ただならぬ雰囲気とどことなくユーモアがあって、なんか面白いの。最初にも言ったんですけれども、すごくリアリティのある問題と、それに加わった別の要素っていうのが両方あることによって、見る人もその中にすぐ入っていけるっていうか、なんかこう余裕ってゆうか、生まれてる感じは感じました。
染井:確かにそうですね。“悲しい”を悲しいで変換するよりも、絵としてイメージとして落とし込みたい、見た人に完全に伝えたい気持ちがあんまりないと言うか。その人の頭の中であるようなことを描きたい気持ちがあって、みんなが分かる形にしたいっていう気持ちもちょっとあるかもしれないです。
光田:池崎さんはこの最初の辺のパート、またもっと拡張してもいいんですけど、この作品について語りたいというのはありますか?
池崎:今、染井さんからお話を色々聞いて、3人の会話の中で聞いてなかった深さの話を聞けたなと思ったんですね。言えることと言えないことっていっぱいあるんですけど。こっちの赤白帽子は小学校で撮った写真で、数年前に自分が小学校の校門の前を通った時に、ちょうどこんな感じで小学生の男の子が赤白帽子と体操服で裸足で学校の校門からふらふら出てきた子がいて。ちょっとびっくりして「どうしたの」って聞いたら、何も喋らなくて「でもほら危ないから学校に戻ろう」みたいな感じで言って腕を掴んだら、すごく本当に戻りたくないみたいな。いやだって言われて、学校いやなんだなって強く伝わってくる体験があって。
その頃個人的にも親として学校って難しいよねって思う出来事がちょっとあったんで、そのことがすごい心に残ってて。印象的な出来事だったんですけど、それを今回学校で撮影できるってことになって、再現してみようかなって思って撮った写真です。
光田:再現すると感じるところありますか?
池崎:ありました。私が実際体験した時は門の外から見ていて、なんで心に残ったのかなっていうと、それは子どもにとって現実の世界って学校と家がベーシックだと思うんですけど、学校にいるのが嫌ってなると、行き場がない、心休まる場所は家しかないだろうし、でも多分家庭でも学校に行けないってことでみんな悩むだろうし、小さい社会の中で生きてる子どもって状況に対して、やるせないみたいに思ったんですね、現実の中に行き場がない感じに。
でも今回これを作品化するにあたって色々考えて、今回は無意識的に門の内側から撮ったんですけど、そう見るとこの門のところで、その子にとっての現実と、そうじゃない別の現実の可能性っていうか、場所の境界線みたいになってんのかなと思って。外から大人の目線で見たら行き場がないと思ったけれど、中から見たらいや実はそうじゃなかったのかも、っていう希望みたいな風に解釈できたらなって思いました。
光田:なんかね、緑が全体にあって、その写真の真ん中に赤い帽子があるってすごい印象的な……これはどういうイメージなのかっていうのはうまく言葉で説明できないですけど、その扉の間に挟まっている、行くか戻るかみたいなその緊張感と、この色彩の綺麗さがね、すごく不思議な効果を出してるなと思いました。
池崎:ありがとうございます。
光田:全体的にそうなんですけど、その……攻めてる感じがね、ありましたね。攻めてる感については後でまた言いたいと思いますけど。佐藤さんはどうですか?
佐藤:この壁で言うと、展示の一番最初にある写真(No.1)が私にとってはこの3人の制作で初めに撮った写真で。なぜ人に見せようという写真は言葉をある程度まとめてから撮ろうとするかと言うと、撮る自信がないからで、考えないで行って撮れるのかなっていう不安があったからなんですけど。
今回ほぼ考えないで撮るということをやってみて、撮影の時点では分かっていなかったことが、後々こう自分の中の……なんだろう……生い立ちからくる考え方とかに繋がるところがあるなって気づいたのが1枚目の写真です。あの写真はニュータウンで、同じデザインの家が並んでるような綺麗な街、意図的に作られた完璧な街という所で撮りたいな〜となんとなく思って撮影した写真で、それが自分の生い立ちの生活空間とか、家庭環境とか、私も母子家庭で育ったので、そこにすごい乖離と憧れがあって。あとそういった場所に嫌悪感というか気持ち悪さというか、これは妬みが入ってると思うんですけど、そういう違和感みたいなの、ちょっと未だに言葉としてまとまっていないですけど、この写真に関してはそんな感じがあります。

No.1「my family_1」2020、佐藤麻優子
光田:そうですね。違和感っていうのは何か会場にあるような気がします。何かこう引っかかりみたいな。一見すごい日当たりよく写ってるんだけれども、これが最初にその感じを掴んだ?
佐藤:そうですね。2人に立ち位置や服も指定してるんですけど、こうやって持って欲しいとか。赤ちゃんみたいな、あれ赤ちゃんじゃないけど。指定している時は何でそうして欲しかったのか、その指示を出したのか、意図的ではなかったんですけど、後から展示になった時や3人で話しているうちに気づくことがあるっていう体験も自分の中では新鮮でした。1人の時は少ないので。
光田:あれ出てきますね何度かね、赤ちゃん。
佐藤:そうですね、2回出てきてます。
光田:その布の塊を抱くっていう。
佐藤:そうですね。
光田:それは、これは何度か出てきてるんですけど、佐藤さんのイメージとしてやってみたってことですか?
佐藤:そうですね……。役割に対する疑問みたいなものも入ってるとは思うんですけど、親とか娘とか家族ってなんだろうな。親も人間で、ただの一人の男の人で一人の女の人だけど、子どもから見た時に親っていう生き物みたいに見える時期というか、人によってはあると思うんですけど。そういうものに対する違和感が母子家庭だったから余計なのか、子どもの頃からなんか変、変な感じがしてて、その時の気持ちも入っているかもしれないです。正直この写真についてはまだ、あまり自分でわかりきっていないかもしれない。
光田:このイメージはこの展覧会にとって大切ですね、布の赤ちゃんのようなものを、自分で抱えた側の池崎さんや染井さんは何か感じることありました?
染井:佐藤さんの洋服を貸してもらって私が娘役だったり、池崎さんの洋服でお母さん役やったりしたんですけど、なんだろうな、普通の人としてこういなきゃいけないなって思って。この空間に住んでる人としていなきゃいけないと思って、撮影する時立ってたんですけど、なんかきもいなって思った。(この住宅街が)スタジオみたいな感じだったんで、誰もいないし違和感があって、気持ち悪いなみたいな感覚はすごい共感しましたね。でもこういう風に作品として撮ってみた時に広告写真みたいにも最初思えて、どういう感じで佐藤さん撮られてるんだろうなって思ったんですけど。後からじわじわ気持ち悪さみたいに感じるようになって、すごいかっこいいなと思って。そこまで到達するのが自分は長かったから、すごい早いなって思いました。
光田:ここの会場の構成は佐藤さんがだいたい考えられた?
佐藤:基盤になるものを自分が作って、それにみんなから意見をもらってこの形になりました。搬入してから実際に観てみると違うなって思うところを入れ替えたりもしています。
少し話が戻っちゃうんですけど、自分の写真の布の赤ちゃんを持ってもらっている時に池崎さんが、本当に赤ちゃん持っているような感じがしたと言ってたのがとても印象的で、それを思い出しました。染井さんが撮っている傘をさしてる池崎さんの写真(No.5)も、撮り終わった後に池崎さんが、階段の段差のせいもあると思うけど私のことを自分の子どもみたいに感じたと言っていて結構びっくりしたことを覚えてて、ちょっとそのことを聞きたいなって思った。

No.5「by the side」2020、染井冴香
池崎:そうですね、出かける時ってやっぱり子ども小さい頃だと一緒が多いんですけど、そういう時と比べてやっぱり撮影は感覚がすごく違って。私撮影中は、素っていうか、設定されたシチュエーションに入り込んだりしないんですけど、でもあの時に、染井さんの衣装とかがすごい絶妙で、コーディネートみたいのが凝ってて、小道具とかもすごいんですよ。二人が着替えして見た瞬間、わっ、不思議な雰囲気だなあってその時思ってて。
そこで撮影している時に、ふとあの階段に立っている時に、前に立ってるの佐藤さんなんですが、自分の娘といる感覚に一瞬なって何かこうパッと世界の感覚が違うって言うか、やっぱり親として自分がいる時の世界との関係と、そうじゃない時の関係って自分のアイデンティティによって世界ってすごい変わるなって思いました。
光田:見所がたくさんある。いろんな写真というか、大きさもそうですし、組み合わせも、2つの写真を並べたり、関係ある写真の間に関係がちょっと違う写真入れたりとか。こういう構成は、みんなでかたちにしたんですか?
佐藤:そうですね。最初に3人でどう展示をまとめるかってなった時に、壁を一人一人分けるという話もあったんですけど、でもなんかそれがやっぱりしっくりこなくて。一見誰の写真かは分からなくなっている方が自分の中にすっと入ってくる感じがあって、そのようにしました。なるべく違和感がそこでは出ないように、流れを意識しました。
光田:並べ方ってすごく大事だと思うんですけど、3人の意見はぴったりだったんですか?
池崎:そうでもなかったですよね、最初は。最初本当になんかどうするみたいな感じで、想像がつかなかったんですけど。3人で誰がリーダーってないんで、その何かをまとめようってなった時に意見が割れそうだなって想像すると「あ、どうしよう」みたいに悩んだりとか。でも今回は展示に関しては展示リーダーを決めようって提案していただいたんで、佐藤さん主導で作っていただきました。
光田:並べ方によって違った写真展になる可能性はすごくありますよね。これだと特にそう思ったんですけど、赤ちゃんを抱っこするとか、池崎さん達が親子に私も見えたんですけど、親子に見えるとか、小学生みたいな感じだとか、家族の問題みたいなことが感じられながら、この扉の上に、蜃気楼じゃないけど、水に映ったファミリー住宅というか、それがあった後に、またちょっとここの壁からは感じが変わってるなっていう風に思ったんですけど、それでいいですか?
佐藤:そうですね。家族から学校を交えつつテーマが流れていっています。ただこの染井さんの作品2点(No.18・19)までは家族と学校のエリアに入っていて。私この染井さんの写真はまだ具体的に聞いたことがなくて、変身と家族と……どうなんだろう。

No.18「family」2021、染井冴香

No.19「The fake」2021、染井冴香

染井:これ佐藤さんの実家の跡地で撮るってなった時に、佐藤さんがさっきおっしゃってたと思うんですけど、親は親って見てる時期と、その親が「あ、この人って一人の人だったんだ」というか、女性だったんだとか男性だったんだって思えるのが佐藤さんよりは全然遅かったと思うんですけど。
家族を一人一人の人間って見てて、今も全然そういう風に関わってるんですけど、本当に血つながってるんだけどすごいバラバラっていうか、家族も一人一人だなぁ、人間だなぁって思ったり、同じ種族と思えなかったりする時があって。それって別におかしいことじゃないし、家に過ごしてる時間って意外とそんなにないし、お母さんがパートで働いてたら8時間はいないわけだし、そういうことの変さ見たいのが結構面白いなと思って、それを落とし込みたいなって思って。
光田:そうなんだ。……そうなのか。
染井:役割みたいな、一人一人の役割じゃないけど、そういうのがあるなと思って作ったやつです。
池崎:前会話している時に、さりげなく染井さんが父親ってキャラクターだからという一言を言ってて、その時はわからなかったんですけど、でも何回も後から読み返したら、「あ、そういうことか」ってなんかすごいハッとしました。
光田:この辺りから私はより攻めた感じがしてまして、その攻めたっていう言い方はあまり綺麗な言葉じゃないかもしれないんだけれど、ストラッグルっていうのかな、何かのイメージを表すというよりも、イメージを獲得する方に向かって体を動かすみたいな、そういうことが自分には感じられてます。これが何をしているのかとかはパッと見たぐらいじゃわからないんですけども、例えばこのベッドサイドで3人が色々なことをしているその前後の写真(No.21)、花の写真(No.20)と花を持った佐藤さんの写真(No.22)とか、この辺りも何かのイメージを演じるとかではなくて、イメージを捕まえに体を張るみたいな、どうですか?

佐藤:今光田さんが言ってくれて、自覚的ではなかったんですけど、すごいそうだなって思って。この3点の写真は、割と無理して撮った写真です。染井さんがトラウマについて撮ってみようと思ってるって話になって、それまでも家族について撮ってみようとか、誰かから提案まではいかないけど提示があって、そこに2人が乗っかる形で作ってきて。トラウマかぁなんだろうと思い返した時に、自分でも忘れようとしていた、写真にもしてなかったぐらい嫌だったことが、自分の場合は性的な事だったんですけど、それを初めて写真にしてみたのがこの3点で。
撮り方もわからないし、本当に探り探りと言うか、できたのかできてないのかもわからなかった。会場設営後に染井さんと数時間キャプションを書き直したりしている時間があったんですけど、その時にやっとできた感じがしたというか、タイトルとキャプション込みでなんか……なんだろう……落ちたというか、落ちるところが決まったって感じの写真だったかな。
光田:これは佐藤さんの作品だけれども、こういう風にしてっていうようなはっきりしたディレクションとはちょっと違う?
佐藤:これは結構はっきりしてましたね。
光田:やってみて写真として壁にかかっているのを見るとどうですか?
佐藤:そうですね、先程光田さんが作品にユーモアを感じるって言ってくれたことがすごく嬉しくて。着地できたかな、と感じています。今回、写真の軸となる部分のエピソードは3人とも明るくない話が多いと思うのですが、自分の中で特にこれが明るくなくて。笑い事にしてしまいたいという気持ちがすごく強くて。でも最終的に無理だと諦めて諦めたら受け入れられたというか。染井さんの生まれ変わったという話に通じるけど、受け入れることにより作品も自分の気持ちも着地した感じで。
光田:そういう佐藤さんのプロジェクトっていうか作品に参加したお二人としては何かコメントありますか?
池崎:そうですね、撮影のその場では結構淡々としてて、撮影のテーマに対して凄い深い思いがあるんだなっていうのはひしひしと感じてたんですけど、でも私たちの距離って、友達っていう親近感でもないし、でも写真が本当に軸にあって。制作をするという目的があるんで、それがあるからこそ言えることもあるし、語るということもあるけど、絶対踏み込めないなっていうのもあって。
そうですね。その撮影の日は確か佐藤さんは最初の待ち合わせで会った時からいつもと雰囲気違うなと思ってて。今考えると距離を感じてて。その辺の深さっていうのは写真撮って出来上がってみて写真についてミーティングして、でその後もどんどんその過程の中で撮影の後から作品になるまで、なってからも、どんどんこう変化するっていうか。いろんなことが分かってくるっていうのが私の写真の受け取り方ですね、はい。本当にこれはいろんな深い事があると思います。
染井:イメージ的に撮っててもそうだったんですけど、私がその時期に魔女の映画を見てて、魔女って言っても全然ファンタジー的な魔女じゃなくて、現代にも本当にいるんだよみたいな体の魔女のやつに似てて。本当に佐藤さんが作品について撮影の後にお話しくれたとき魔女みたいに撮ろうとしたと言ってくれた時に、魔女が誕生してるみたいだなと思ってたから、力とかないかもしれないけど「すごい、ぽいなー」って思って、良かったです。
光田:染井さんが魔女のように見える写真もいっぱいありますね。魔女っていう言葉は何かイメージありますか?
染井:魔女って昔から比喩的な意味で捉えられてるじゃないですか。でもそれって別に全然使っていいなって思ってるかもしれない。いてもいいかなみたいな。ファンタジーじゃなくって「あ、この人魔女だな」って思う時あるから。全然魔女だなって思います。
光田:魔女っていう言葉で、現実のリアルのレベルと少しずれた何かがありそうですね。なるほど、じゃあ後半の作品について言ってみたいことがあったら教えてもらいますか?最後も攻めまくって終わるって感じが、反応して攻めるっていうのはつまりストラッグルっていう事ですけども「いやぁ、ストラッグルしてるぞ」って思って、すごく面白く見たんですけれども、これについて話したいっていう作品を選んで話してもらえますか?
佐藤:最後の壁に行く手前なんですけど、自分の花の横の写真(No.23)が、この展示の中で誰の写真かっていうところの抽象度が高い写真だと思っていて、ちょっと池崎さんに話聞きたいかな。

No.23「your nose, your gaze」2020、池崎一世
光田:そうですね。
池崎:鼻をつけた写真なんですけど、あれは学校で撮っていて。染井さんの撮影のためにその場にいて、染井さんのディレクションで染井さんの空気っていうか、舞台の中に私たちがいて、その風景を佐藤さんはちょいちょいスマホとかで、すごい上手く知らない間にいろんなスナップショットを、いつも撮ってくれたりするんだけど、動画とかも。でその時も撮ってたんで、自分のフィルムのコンパクトカメラで撮ってほしいなと思ってお願いして。
私佐藤さんのポートレートってすごい特徴があって好きだなと思ってて、佐藤さんに撮ってもらったんですけど、出来上がってみたら、やっぱり佐藤さんのポートレートの眼差しってあるなと思うんですけど、それを自分がしてるなと思ってて。鼻やその舞台自体は染井さんのシチュエーションだったんで、自分のカメラで自分が写ってる写真だけど、私別に何もしてないなっていうか、写真見たら混ざってるなって思って。
光田:それは、3人が?
池崎:そうですね。同時に空っぽみたいにも見えるなと思ってて。セルフポートレートっぽいんですけど、セルフポートレートは自分の前の作品とかでも撮っていてそれは自分が自分であることがよくわかんなくって確認するみたいな動機があったのかなと思うんですけど、撮ってみて写るとやっぱり自分ですけど、同時に写真になるとちょっと違う、結局誰でもないみたいな。人って別に、自分は自分だけど結構移ろいやすいというか、確固としたものじゃないなっていうのを写真見るたびに思って。
私、人に写真を見てもらう時に、やっぱ自分があやふやなせいか、写真を見てくれた方自身が、なんとなくでも変に気張る形でなく、ふと腑に落ちるような感じで「自分って?」みたいなことを感じてもらえるといいなって漠然とよく思うんですけど。見た人が自分自身のことを感じるっていうか。この写真に関しては特にその感覚を持ってもらえたらなってことを思いました。
光田:この自分の眼差しは佐藤さんのポートレートの眼差しだなと思うっていうのも不思議でしたし。
佐藤:染井さんが毎回身体をカスタムするアイテムを持ってきてくれてることもあって、全部が重なって3人が合わさっているのに、それこそ空っぽみたいな、なんだろう、アイデンティティを定義出来ない写真なのが、この展示のタイトルにも繋がる部分を持ち合わせているって感じているかな。
光田:面白いですね。つまり池崎さんの話は、作り込んで撮られた写真とは違って、でも3人の色んな要素が入ってるんだけれども、この写真は何してるところっていう風に言い難いところもあって、だからその容器みたいな開いたものというか、そんなようなお話でしたね。それはコラボレーションとしてとっても良い瞬間のように今聞きました。なるほどね。
佐藤:あの時あの場所で池崎さんが撮ってくださいと言わなかったら存在しなくて、それが写真らしいなと思うというか。他のはセットアップだから絵画に近いというか、瞬間性が少ないものが多くて。これはすごく偶然が重なってできた感じがするから、瞬間的で写真だなと感じてる。
光田:それがいい位置に飾ってありますね。やっぱりこの展示は面白い展示だなって思いますね。その切れ目があるようなないような、でもなんとなくちょっとこう壁によって雰囲気があったりとかして。全体を一つの物語のようにも読めながら、いろんな道に入ったり出たりできるような、そんなような展示のイメージがあって。
染井:池崎さん話してほしい……。メインの……。
池崎:あ、メインの写真(No.28)みんなに選んでいただいたんですけど、場所は実家の近所にある森で、子どもが小さい時に、会社に行って保育園で子どもを拾って帰ってくる時に、この森のそばを毎日通って帰ってきて。そこ通ることで日々の昼間の緊張から素に戻ると言うか、そういう場所だったんですけど。そこに2人が来てくれて、私自分の家とか地元にあんまり人を呼びたいと思わないんですけど、何となくそういう距離があって。でも2人が来てくれて、撮影とか前後ひっくるめてすごい嬉しかったなって思ってて。
で、その木は二分心、bicameral mindっていう、古代の人は、意識があまり強くなくて、脳みそが左右別れてて、今で言う統合失調症で幻聴が聞こえるような、頭の中からもう一人の声が聞こえてて、それで社会は総合的に統制されていたみたいな、そういう学説をジュリアン・ジェインズっていう方が唱えてて、その本を読んでる最中に、なんとなく部屋の中に木の人がいるな?みたいな、そういう感覚がしょっちゅうあって、自分の部屋の中に一人でいる時に、その木っていうのは自分と繋がってるんですけど、自分とやっぱりちょっと離れてるところで。
それがいることでものすごく私は安心感、その時はいろんな、生活のことで不安とか、常に不安が強いタイプなんですけど、その不安が和らぐなっていうのがあって。昔ドローイングで描いたものなんですが、それとお二人とで一緒に写真を撮ってもらいたいって気持ちになって作りました。

No.28「bicameral mind」2021、池崎一世
光田:撮ってみてどうでした?
池崎:嬉しかったです。
光田:嬉しい?
池崎:すごい嬉しかったです。
光田:その嬉しさっていうのは、何かイメージを獲得できたような意味?
池崎:そういう写真的な話っていうよりも、ひとりぼっちの所に2人が来てくれたみたいな、多分そういう結構子どもっぽい感覚に繋がるところがあると思います。
光田:これはでもすごいインパクトのある作品ですよね。どういう意味があるのか、この森がどんな森かとかはともかく、でもその中の3人の出会いが何かファンタジー的なものの始まりと違いますけど、ドロシーが風に乗ってバーっと飛んでいって着地して、3人揃ったみたいな。割とそういう不思議な出会いのイメージが自分には感じられましたけどね。どうでしょう、染井さん(この壁の中で)この作品について話したいというのは?
染井:私作品ひとつしかないからないけど、今池崎さんがお話しししてたメインビジュアルの作品についての話がすごい面白いなと思ってて。自分が意識してないところの頭の部分で何か思いついた、思いついたというか、多分あったイメージ……。意味なく撮った感じだと思うんですけど、その撮り方は自分が今回展示する前にやってたことだったなって思って、本当に漠然と一緒だったんだなって感じがすごい嬉しかったです。
光田:今までの染井さんの作品と通じるところがある?
染井:そうですね。制作の仕方が結構一緒なんだなって思って、そこがすごいびっくりしたりしたし、っていう感じです。
光田:3人展のイメージとして非常にふさわしい作品かなと思うんですけど、ここに今出てる作品よりももっとたくさんの作品があるんだよっていう話をさっきちらっと聞いたんですけど、だいたいどのぐらいあるんですか?この何倍ぐらいとか。
佐藤:撮影に行った場所のどれかしら1枚は入っていて、その同じ場所で何枚も撮ってるものを捨てるのが割と大変でした。もっと本当は点数を絞る予定だったんですけど、これも入れたいとか、他の人の写真で入れて欲しいとかがあって、何倍だろう……2倍ぐらい……?
池崎:多分2人は結構あると思う。私はそんなに、結構減らしちゃったらこれで決まりになっちゃったんで、2人はいっぱい持ってると思います。
光田:今は展示なので、大きい写真と小さい写真組で入ってるものと、そうじゃないものってなってるんですけど、もし写真集これで作るとしたら、この展示のイメージで行きますかね?それともまただいぶ変わりますか?っていうのは写真集にしたらいいんじゃないかなってね、勝手に。このまま片付けてしまうのがもったいないくらい面白くて。すいません、個人的な感想ではあります。
光田:ご自身の作品以外で、お二人の作品の中で好きな作品はどれですか?っていう質問を頂いています。今展示している中で、ご自身のではなくて、これが好きだって言うのを1点ずつあげてもらうみたいな感じでいいですかね。迷ってますね、3人ともね。
佐藤:私は染井さんの、染井さんが死んでる写真はやっぱり好きで、後は……二人の写真はほとんど好きなんですけど、池崎さんの写真はやっぱりメインに選ばれてるやつが一番印象的というか、見たことない池崎さんの写真だったので。
ドキュメンタリーなわけではないけど、何だろうな、普段はもうちょっと現実に近い写真が多いように感じるけど、さらに現実から遠い写真だなって感じたから。それって染井さんのプロップの影響とかもあるのかもしれないし、この3人でやったことによって出てきた写真だなと感じるから。その2点が私は好きかな特に。
池崎:私は染井さんのは、屋上の写真(No.17)がすごい好きで、3人並んでいるやつをメインビジュアル押ししたんですけどそれは叶わず。私よく撮影正直けっこうしんどいなってその場では思うんですね。時間がなかったり物理的に撮影って疲れるなっていうのはあるし、ただ写真が出来上がるとその思い出がどんどん楽しくなるっていうのは今回の撮影に関してはめちゃくちゃあって。
その屋上の写真がすごいそれがあって。その撮影の後からどんどんいろんなことが作られてきてって言うの変ですけど、重みが増してきて。やっぱり自分一人で撮ってるわけじゃないんで、写真の解釈っていうのがみんな本当に違うんだなって、その多様性をものすごく実感して、自分一人で撮ってたらその写真について少々見方の変化はあってもだいたい一貫したものがあると思う、でも今回はその見方もそもそも違うししかもそれは同価値みたいな立場で3人で撮ってるから、その移り変わりとか見え方の違いの振り幅みたいのがすごく大きくって。
佐藤さんの写真で好きなのは、あの黒いドレスを着てる私と染井さんが手繋いでるやつとか、佐藤さんは、排他的な意味じゃなく、女の人しかいないパラダイス的なところをイメージして撮ってて。その時はふーんと思ってて、なんとなく写真好きだなーと思ったんですけど、ついこないだ家庭のこととか生い立ちのことを話ししてたら、やっぱり私も普段自分の家庭が一人親だったりとかで、欠けてるなぁみたいな、ちょっとしんどいぁみたいなのを感じていて、でもあんまり普段生活してる時それを意識しないんですよねそういうことって。それが普通だから。
でも何かのきっかけでみんなと会話してる時に、もし一人親家庭でもそれが普通で何も困ることがなくって、家族の形態のバリエーションも、例えば……そのゲイカップルって言い方がいいのかな、も別に普通、本当に日本の社会でそれが普通になったのを想像したらすごくパラダイスだなって思って。その時に本当に佐藤さんの写真の意味がなんかすごいストンと落ちてきて「あーっ」てすごい思いました。

No.17「君の形を知りたい」2020、染井冴香
染井:私もお二人の写真選べないくらい好きなんですけど、この池崎さんの後ろにある花の写真(No.14)が、この画角以外のいろんなイメージがあったんですけど、すごい面白くって。撮影場所は小さいバラ園だったんですけど、私はこの後ろのビルが映らないように世界を収縮して、圧迫して撮ってたんですけど、池崎さんがこういう撮り方してて。ここの場所変で都会の中にいきなり置いちゃいましたみたいなバラ園で。その変さがすごい面白くって、単純に写真の勉強になったっていうのと、とても好きでした。
あと佐藤さんの写真は、2人とも結構画角遠めのやつ展示にする時に、人の距離が割とある写真を多く選ばれてたんですけど、近く撮ってたやつもあって、それもすごい良かったなと思って、次回是非という感じで考えてて。本当に面白い作品が他にもいっぱいあって。
あと佐藤さんのレイクタウンで撮った家族の写真とかも変さみたいなのに気づいた時のはっとした感がすごくあって、自分の作品とかでそういうことってあんまりないから面白いなって思いました。

No.14「Untitled」2021、池崎一世
光田:聞いてるとすごい楽しそうで、やはりいいなっていうかね。今後とかって考えます?今回はまだ展覧会終わってないけれども、この後も制作一緒にしたりするような可能性っていうのはどうなんですか?
佐藤:現時点ではなくて、でも展示に来場してくださった方で、別の展示形式で見てみたいって言ってくださった方がいて、それは確かにやってみたいなと思った。見え方がまた全然変わるだろうなって。さっき言ってくださった本とかもうそうなんですけど、その形で見てみたいなっていうのは個人的にはある。
光田:お二人はどうですか?
染井:さっき光田さんがおっしゃってくれたんですけど、本がこの作品で合うかもしれないなと思って媒体として。ハンドアウトにもいっぱい文字があるし、各々言いたいこともあるけど、言葉から結構始まった、会話から始まった作品なので、だから本とかも良い距離感で見れるなぁと思って、私はいいなと思ってます。
池崎:私は先のこと考えてなかったですけど、でも作ってみたいなと思います。展示とか本とかも全然ありがたいんですけど、撮ってみたい、また一緒に。
どういう風にっていうのはあんまりわかんないですけど、やっぱり色々試行錯誤ですけど、すごく制作してて本当に多面的で気づくことがものすごく多い、展示全体についての見方が自分でもちゃんとわかってないというか正解が絶対になくて、私がこうだと思っても、絶対に同じ重さの2人の見方がこっちにあるっていうのに気づくと、いくらでもいろんなものが作れそうだなっていうか。そのダイナミックさ、ダイナミクスみたいのが面白いなと思うんで。
光田:なるほどね、そのダイナミクスっていうの本当にそうですね。例えばですけどジェンダーとかでの1つのテーマ、大まかなテーマいうのがあるとしたら、1つの視点ではより語りにくいような気がするっていうんですかね。一本道っていうのは引きにくいし一本の線も引きにくいという風にも私は感じるんですけれども、そういう時にこの2人って取るよりも3人っていうこの3がね、その2人だったら線は1本なんだけど、3になるとちょっと線が増えますよね。
その感じていうのがこの作品の魅力にもやっぱりなってるのかなあていうのを今日お話し聞いててすごく感じたんですけど、どうでしょう、他にもご質問ありますか?

ーセルフポートレートの系譜から見えること、あるいはわかることがあればお聞きしたいですという質問をいただいてますが、これは3人の皆さんもどういう風にセルフポートレートを捉えられているのかっていうところだったり、光田さんからもセルフポートレートに関してもしありましたらお願いします。
佐藤:セルフポートレート撮ることについては最初葛藤があったんですけど、女という性別で、セルフポートレートを撮ってる人は女性がなぜか多いっていうこととかもあって。今は少なくなってきたけど、“女性の写真家”として見られることが最初はなんか嫌で、それでやりたくないなって思っていたんですけど、自然に自分の中にあることなのでそれを受け入れて撮るようになりました。
スタートは、人に頼めないなと思うイメージがあって自分で撮らざるを得なくなったというところだったんですけど。自分の場合は、自己の確認というか、形がわからなくなることがあると言うと抽象的なんですけど、自分がどんなものなのかを確認する作業をみたいな側面があるかな。
池崎:セルフポートレートはそんなに最近は撮ってなかったんですけど、佐藤さん言ったみたいに、そもそも私の場合は自分が誰かと取り違えられたりとか、自分が誰だかわかんなくなっちゃうっていう不安がある時期があって、そこが一番モチベーションでした。
染井:セルフポートレートは、私写真始めたばかりの時期に写真史みたいなこと詳しくなくって、今もあまりわからないんですけど、撮る人がいないから自分で写ろうかなみたいな気持ちで、始めて。
基本的に写真写ってる時、あんまり自分を写すみたいな気持ちがないっていうか、その中の人を演じてるみたいな感じなんで。自分じゃなければ自分じゃないほど良いっていうか、そういう気持ちで撮ってます。もう自分じゃなければないほど、そういう風に見えてるやつの方が好きですね、自分の写真は。
光田:変身っていうか、してますもんね。なるほど。今日はいろんなお話聞けてすごく面白かったんですけど、皆さんすごい本音で話してくださって、この写真展を見る視点がまた変わるようなそんなお話だったかなって思って。どうもありがとうございました。
池崎・佐藤・染井:ありがとうございました。





