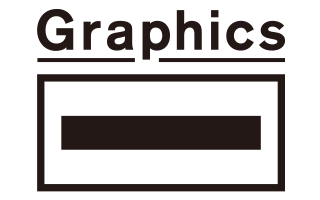檜山真有(キュレーター)
1994年大阪市生まれ。キュレトリアルの実践として「フォールアウトファミリーズ」(2022年)、展覧会「オカルティック・ヨ・ソイ」など。2023年は展覧会をつくります。
Ghost Parade
絵でなく、純度100パーセントのそれ(筆者注:キャラクター)を描きたい。(注1)
彼女の描きたいキャラクターというものは、描くことで現前させたい他者の存在の器のようなものだ。表面上で起こる出来事でありながら、問題は平面上にはない。問題は奥行きとして用意されているキャラクターという概念だ。
キャラクターが見つめる先で彼女「ら」が行うパフォーマンスは、『ゴドーを待ちながら』のウラディミールとエストラゴンの眼差しよろしく誰に向けられるわけでもない人格(キャラクター)不在である他者の存在の器に向けられる。しかし、かといって首から上の想像力で充分に現実を滞りなく過ごし、楽しむことのできる現代の私たちはそれを不条理だとは思わずに、もはや古いというかどこか懐かしい。
佐川梢恵、森野真琴展「明日天国を離れる ― I leave heaven tomorrow」は佐川梢恵と彼女が架空の他者として設定した森野真琴との展覧会だ。しかしながら、本展では森野真琴は現れることはなく、展示室中央に据えられている木箱に森野真琴の存在が託されており、森野真琴を境に、佐川によって描かれたマンガ絵の人物画のある空間と、居住空間を模した空間に展示室が分かれているように見える。
「蛍の光」が流れたら布団の中にいる佐川がある一定の動作を行う。靴下を穿き、水を飲み、洗面台で髪を梳かし、馬を軽く散歩させ、掃除をする起床時のルーティーン。彼女はそれを終えるとすぐさま布団へ戻る。1時間のうちに数回は行われる短いスパンのパフォーマンスから、そのインターバルにある布団の中にいる彼女まで、マンガ絵の人物画たちは彼女らに視線を注いでいる。
異質でありながらも締まりのないふわふわとした鑑賞体験は、コミュニケーション障害(=コミュ障)が悪気なく巻き起こす寄る辺ない空気とよく似ている。ためらいがちな微笑みや、誰も応答せず流れる沈黙の気まずさは、佐川と森野真琴、「アニメ絵」の距離感を微妙なものにしている。彼女は自分が作り上げたものとでさえ、視線を合わせず、どことなく謙遜しあう関係性をつくりあげる。コミュニケーションのままならなさが主題である本展でこのような空気感を醸し出せるのは、彼女がよっぽど切実であるか、あるいは、全くその逆であるかだ。しかしながら、どうしたって不器用で遠回りな方法でしか、コミュニケーションを図ることができないとしたら、この先どうやって生きていけばいいのだろう。

目覚めよ我が霊、心励み、明日、天国を離れる。会場にちりばめられた種々の記号は彼女の生活感と宗教的な意味合いを持つシンボルがないまぜになり、ひとつひとつに意味を与えて繋げていくと「選択の中で不安に思ったり、揺れている」ようなどうとでも読み取れるナンセンスなものにしかならないだろう。それは惹句として未だに人気の「良い子は天国に行けるけれど、悪い子はどこにでも行ける」と同程度の口あたりの良さと中身の無さである。天国を離れるというのはどちらでもない堕天の行為だとしたら、堕天使こそどこにでも行けるのではないのだろうか、悪い子は天国にだけには行けない。
だが、本展で堕天を試みる作者は、布団の中でねむり、ほんの少しだけ起き上がり、どこにも行かない。同じ時間をなんどもループして、でも、結局どこにも行けないのは、他者の眼差し、しかも自分で設定した架空の眼差しだったり、自分で作り出した内面化した眼差しが私を見つめてがんじがらめになるからである。だとしたら、振り切ってどこにでも行けるようになるまであと少しだ。A4の紙で自分の世界を描き切っては、つなげて広げてゆくしかない。
佐川の描くマンガ絵の人物は、アホ毛がなびく髪とは関係なく旋回し、みな同じ顔で微笑む。だが、首から下は頭身のバランスは歪み、人間の身体というよりかは肉付きの良いデッサン人形である。瓜、蛇、赤子、杯、水、布といった意味深なシンボルを持つもの以外、手のやり場がおぼつかなく描かれる彼らは、表情筋と二の腕から指先までの筋肉をうまく扱えないコミュ障の私たちでもある。
目を見て、口で言葉を発して、コミュニケーションをしないことが不自然でなくなった昨今、コミュニケーションが苦手であることが最も現れるのは「手」である。私たちは顔も名前も知らない人のことを知るために、もはや手を使わなくて良い。手紙やメールを送らなくとも、あらかじめ書かれたプロフィールを読めば、お互いのことが分かった気になるし、触れなくとも存在をなぞることができる。むしろ、私の手は他者とコミュニケーションをとろうとすると空回りして、自然に振舞おうとすればするほど、指先はだらしなく緩んで、腕の筋肉は中途半端な力み具合で垂れ下がり、収まりは悪い。
腕に力がぎゅっと入るとき、ペンを握るとき、コップを落とさないように持つとき、自分自身のことを悔しいとか思うとき。腕の筋肉を他者に向けては上手に使えない私たちでも、自分自身を守ったり、自分自身を表現するときには筋肉は緊張し、自分の思う通りに動かせる。別の頭を使っている。私はもう独りよがりなんかじゃなく、本当に一人で生きていけそう。
(注1)…2022年10月6日に行われたトークイベント「ハリボテの天国から、なぜコミュニケーションに願いを託すのか」室賀清徳(編集者)×佐川梢恵、森野真琴 佐川梢恵の発言より。